
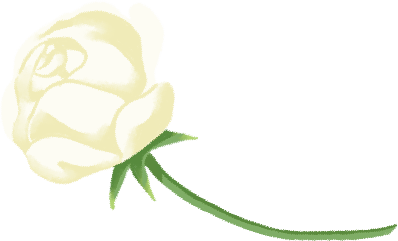
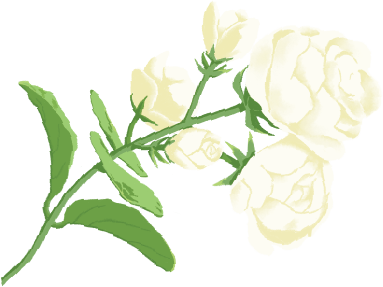


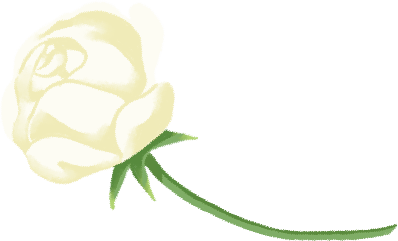
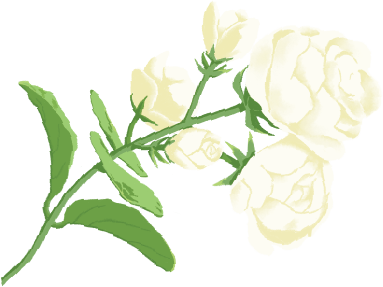


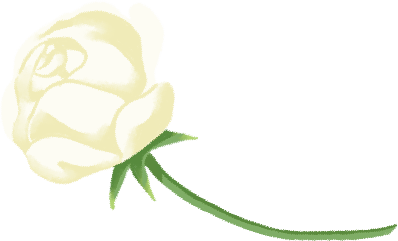
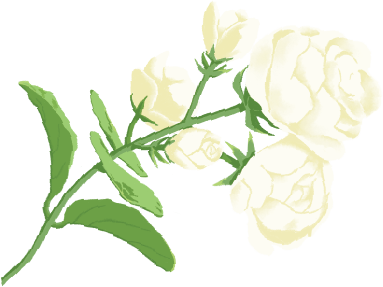


一口飲むと、ジャスミンの爽やかな花の
香りがふわりと広がるさんぴん茶。
昔から沖縄の家庭で愉しまれている、
うちなーんちゅに愛されてきたお茶です。


首里城の復興に携わり、
伝統を未来へ継承していく人たちを
沖縄伝統茶である
さんぴん花茶は応援しています。
日々のお茶時間を通して
沖縄の文化を紡ぐ想いを紹介します。





大宜味村喜如嘉出身。幼少期から祖母の芭蕉糸づくりを見て育つ。沖縄県立芸術大学で染織、イギリス留学で生地製作を学び、40代で琉球大学大学院へ進学。歴史学を専攻し2024年に博士を取得。首里城で被災した染織資料の複製などを中心に様々な調査研究に尽力している。

沖縄の染織の製作研究を行う中、首里城基金を活用し、火災で被害を受けた紅型や織物の復元製作も担当しています。何百年も色褪せない顔料や染料の染め方、素材の組み合わせ方など、琉球王国時代に確立された素晴らしい技術の多くは、明治時代の琉球処分で失われてしまいました。それを科学調査や文献調査で解明し、現代の技法に取り入れて生かすのが私の仕事です。

琉球は諸外国との交易を中心に栄えたので、多くの文化や技術が入ってきました。その中で、沖縄の気候風土や文化、教養に合うものだけが選ばれ発展し、伝統として根付き現代に残されています。さんぴん茶もきっとそうでしょう。伝統工芸品も高級品としてだけでなく、お茶のように現代の暮らしに欠かせない、身近な存在として残して行ければと思います。

喜如嘉の実家ではさんぴん茶と黒糖が毎朝の“おめざ”でした。今でも休憩や食事の時など、1日に何度もいただきます。すっきりした味わいなので、こってりした料理にも甘いおやつにもよく合うし、ジャスミンの香りで爽やかな気分にもなれます。琉球王国時代の人たちも同じように爽やかさを好んで飲んでいたのかなと思うと、親しみが湧いてきますね。

昭和27年に与那原町で創業。先代から受け継ぎ、現在は親子2代で瓦製造に従事。屋根以外にも壁や庭などもっと身近に赤瓦を活用する商品の開発を積極的に取り組んでいる。

復興で使用する赤瓦は与那原町の瓦工場3社で製造しています。与那原は昔から赤瓦の産地。今回も全て与那原の工場でつくることができ、本当に誇らしいですね。当社は土をつくる整土と施工も担当しているので、一貫して関わらせていただいています。土をつくり、瓦を焼き、現在は屋根葺きの段階。正殿が復興する様子を日々実感することができています。

平成の復元の瓦と令和の復興の瓦では、原料が大きく異なります。同じ土が手に入らないという問題もありましたが、火災にあった瓦をパウダー状にした「シャモット」を加えることが一番の難題でした。本来は加える必要のない素材ですが、平成の復元に携わった職人たちの想いを受け継ぐため還元しました。苦労しましたが、いい瓦ができたと満足しています。

瓦葺きの現場では十時茶・三時茶の時間に必ず休みますが、休憩だけでなく、棟梁から多くを学ぶ貴重なひとときでもあります。昔はやかんで沸かしたさんぴん茶を飲んでいました。お茶の時間は自然と会話が生まれるので二人でもよく話をします。意見がぶつかることも多い仕事の話は、お酒の場になると不思議と合います(笑)。飲み物がもたらす時間が関係を円滑にしてくれていますね!

民俗学を専門分野とし、沖縄国際大学大学院修士課程終了後、沖縄県教育庁、公文書館職員を経て現職。沖縄の村落風水や工芸品の研究のほか、琉球産の弁柄の調査を進め赤色の再現に尽力。

私は沖縄美ら島財団の研究室に所属して、琉球王国の工芸品や庶民の生活に関わる内容を専門に研究しています。その一つに、琉球王国時代に使われていた塗料の調査研究がありますが、これが平成18年から始まった首里城の塗り直しに役立てられていたんですね。古い文献を探して、塗料の種類、仕入れ先や製造元を探すなどの作業を進めていました。

当初の計画ではかつての首里城の赤色に近づけるために少しずつ塗料を試す予定でしたが、火災が起き、復元のために未解明だった部分の研究も急ピッチで進めることになったんです。その中で、塗料の原料には沖縄の自然由来の成分が使われていたと分かり、その成分の採取から塗料への加工、塗装までを何度も繰り返し、かつての赤を探ったんです。

首里城の赤色は、火災前に見ていた色とは少し違うと研究の中で分かり、関係者で本当に試行錯誤して今回の赤色を生み出したので、公開時の反応が楽しみです。仕事で行き詰まった時は、さんぴん茶を飲む時間には安らぎをもらっています。小さな頃によくお使いで買いに行ったお茶ですし、県民にとっては親しみがあって飲むと安心できるものですよね。

那覇市首里出身。首里城公園の売店販売員として働き始め、その後、解説員に応募し「沖縄の歴史を伝える仕事をしたい」という夢を実現。お客様と首里城の魅力を共有することを心から楽しむ。

首里城で働くことを決めたのは、海外留学をした時に、沖縄の歴史を全然知らないことに気づいたからなんです。自分の生まれ育った場所の歴史をきちんと自分の言葉で伝えられるようになりたいと、解説員を目指しました。3ヶ月の研修では知識の習得とガイドの実地訓練を受けて、いよいよお客様の前に出ることになった時はやはり緊張感がありました。

実は私が解説員になってすぐに首里城火災があったんです。火災前日、最後のお客様をお見送りし、東のアザナから首里城正殿を眺めたのをよく覚えています。まさか翌日にその姿が見られなくなるとは夢にも思わずに。しかもその後はコロナが大流行。しばらく解説員の仕事はできませんでした。だからこそ、今お客様と会えることがとても嬉しいです。

解説員をしていると、沖縄の風習についても質問いただきますが、そこで「小さい頃はおばぁが家でいつも沸かしてくれて一緒に飲んでいましたよ」と実体験を話すととても喜ばれます。自分にとっては当たり前の、何気ない日常が今の仕事に役立てられることはとても嬉しいです。うちなーんちゅだからできる案内を、今後もしていきたいですね。